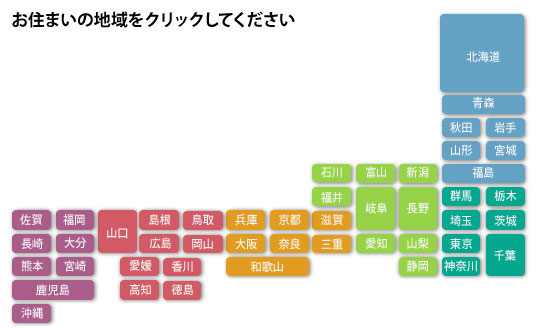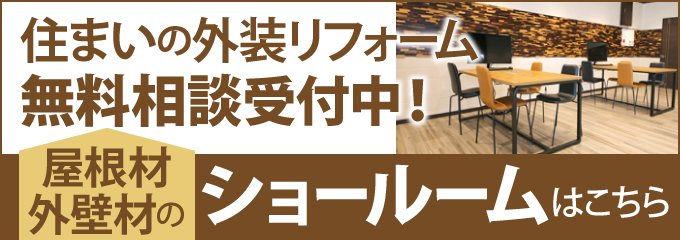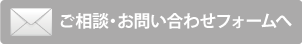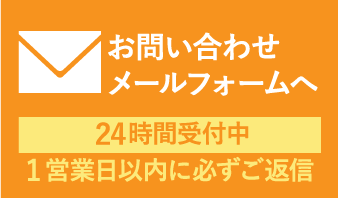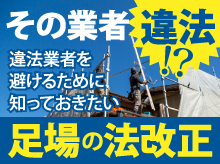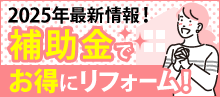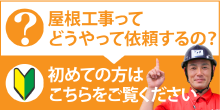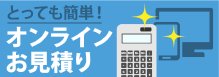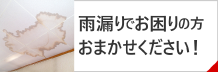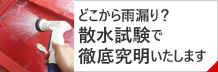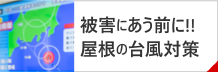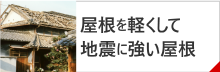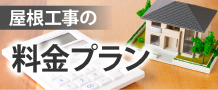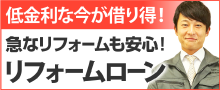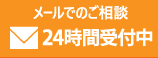この夏の休暇中のお出かけ先はもう、お決まりになったでしょうか。神社に訪れるという方はその前に予習をしておくと、何かと役に立ちますよね。一緒に訪れた家族や恋人に尊敬されることにもなるでしょう。神社の発祥や成り立ち、お近くのお食事処などはガイドブックにお任せするとして、私たちは屋根やですから神社の屋根に関する豆知識をご紹介します。
上の画像は伊勢神宮にある建物です。この切り妻屋根の先端についている角のような部分を千木と言います。これは昔、屋根を建造する際、木材2本を交差させて結びつけ、そのまま残した名残と言われています。
屋根の棟に対して垂直に取り付けられている丸太のような木材は鰹木と呼ばれます。これは形状が鰹節に似ていることが由来になっていると言われています。
神社と仏閣の建築様式は似ているようにも見えますが、実は大きく異なります。最も特徴的なのが屋根で神社の建築様式では本来、瓦は使われません。逆にお寺は瓦が好まれて使われるようです。これは仏教伝来とともに瓦ね伝えられたからだと言われています。靖国神社では瓦も使われていますが、それはとても珍しいことなのです。こういった歴史的背景の影響を受けているのも屋根の面白いところですね。